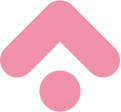「学校に行きたくない」意外に見落としがちな理由とは?対応や相談先も紹介【専門家に聞く】

子どもが「学校に行きたくない」と訴える、いわゆる“登校しぶり”。どう対応したらいいのか、親だけで抱え込んでしまうこともあるかもしれません。
「お子さんのSOSをキャッチしたお父さんお母さんも、誰かにSOSを出していいんです」と語るのは、児童精神科医であり、自身も子どもの不登校に向き合ってきた経験を持つ“さわ先生”。
今回は、登校しぶりの意外な理由と具体的なサポート先について、さわ先生にアドバイスをもらいました。
意外に見落としがちな「学習面」の悩み
夏休みなどの長期休暇明けは、子どもが「学校に行きたくない」と訴えることが多くなる時期です。
数日でおさまる場合もあれば、数週間続くこともあるため、学校を休ませることに抵抗を感じたり、理由がわからず対応に悩まれたりする保護者の方が数多くいらっしゃいます。
子どもの「登校しぶり」精神科医に聞く5つの対応をCheck!
登校しぶりの背景にはさまざまな要因がありますが、なかでも、意外に見落とされがちなのが「学習面のつまずき」です。
たとえば、算数のように知識を積み上げて学んでいく教科の場合、わからないところをそのままにしてしまうと、次の授業もわからないまま、どんどん授業が進んでいってしまいます。
結果、さらに内容がわからなくなり、算数の時間が苦痛になってしまう。そこから学校が嫌になって、登校しぶりにつながることは珍しくありません。
親としては、お友だちとのケンカやトラブルなどが原因では? と人間関係の複雑な問題に意識が向きがちですが、じつは、こうした学習面で困っているケースも意外と多くあります。
普段からお子さんとコミュニケーションをとり、学校であった話を聞いたり、一緒に宿題の内容を確認したりしながら、何に困っているか探ってみましょう。
困ったときに頼りたい5つの相談先
実際に子どもの登校しぶりに対してご家庭での対応に困ったら、積極的に学校や外部のサービスを頼るのもひとつの方法です。
ここでは5つの相談先をご紹介しますので、連絡しやすいところからぜひ話をしてみてください。専門家の力を借りることで、よりよい解決策が見つかることがあります。
1.担任の先生
お子さんの学校での様子がわからないときや、家庭内で解決することが難しい場合は、学校と連携をとりましょう。
担任の先生に相談することで、学校での子どもの様子を把握したり、今後の対応を一緒に考えたりできます。
学習の遅れが原因で集団生活に馴染めない場合は、「特別支援学級」や週に1回程度個別の指導を受けられる「通級指導教室」の利用を検討することもよいでしょう。
2.スクールカウンセラー
学校に常駐している、または定期的に来校する「スクールカウンセラー」も心強い存在です。

子どもの話を聞いてくれるだけでなく、保護者自身の相談にも乗ってもらえます。第3者に話を聞いてもらうことで、客観的な視点が得られたり、心がスッキリしたりすることも。
予約制であるケースが多いため、日程を確認してみてはいかがでしょうか。
3.教育支援センター
「教育支援センター」は、自治体が運営する公的なフリースクールのような施設です。
もともとは適応指導教室という名称でしたが、2003年から徐々に教育支援センターと呼ばれるようになりました。
学校に行きづらい子どもたちに向けて、自分のペースで学習したり、活動したりできる場を提供しています。
4.児童相談所
「児童相談所」というと虐待の相談先というイメージが強い人もいるかもしれませんが、そんなことはありません。
子どもに関する悩みすべてに対応してくれる場所であり、子ども本人・家族・学校の先生・地域の人など、誰でも相談できます。
児童福祉司、児童心理司、医師、保健師など、さまざまな分野のスペシャリストがいるため、多角的な視点から助言を得られるのが大きなメリットです。
5.医療機関

不登校だからといって、必ずしも医療機関を受診する必要はないと私は考えています。
けれども、眠れない、食べられない、元気がない、さらには、死にたいなど、心身に明らかな不調が見られる場合は、「児童精神科」などの受診を検討することもぜひ視野に入れてもらえたら。
お腹が痛い、気分が悪いなどの症状を訴えて小児科に行ったけれど、体に異常がない場合も同様です。
親以外との関わり方も視野に入れてサポートしよう
不登校の子どもに親以外の大人が関わる場合は、特別な配慮はせず、いつも通り接するのが一番。腫れ物に触るような態度は、かえって子どもの心を傷つける可能性もあるからです。
つい理由が気になってしまいますが、「どうして学校に行かないの?」と無理に聞き出すことが、子どもの負担になることもあるので注意しましょう。
せっかくコミュニケーションを取るのであれば、「最近どんなドラマを見てる?」「好きなアイドルはいる?」といった普段通りの会話をして、子どもが安心できる雰囲気がつくれるといいですね。

また、子どもが望むのであれば、無理のない範囲で社会とのつながりを持つ機会を設けることもおすすめです。
習い事や親の職場、友人知人、親族など、家庭や学校以外に接点を持つことで、新しい世界が広がることも。
気が進まないのに無理に外に連れ出したり、人と会わせたりするのは逆効果になってしまうため、子どもの様子や状態に合わせて対応できるといいですね。
大切なのは、親自身も一人で抱え込まないこと
不登校はその子の成長過程のなかで、生まれ持った気質や特性と環境が合わなかったために起こることも多く、親のせいでも子ども自身のせいでもありません。
しかしながら、子どもが不登校になると、「どうしてうちの子だけ」「私の接し方が問題だったのかもしれない」などと自分を責めてしまう親御さんがたくさんいらっしゃいます。
実際にパートナーから「甘やかしすぎているから、不登校になるんだ」と責められ、追い詰められてしまうケースも少なくありません。
正解がないからこそ、負のループにはまってしまいがちですが、私自身の経験で言うと、長女が不登校になった際は、学校や各機関、同僚の精神科医や同じ境遇の先輩ママさん他、とにかくいろいろな人に相談をしました。
具体的なアドバイスをもらえることもありがたかったですが、ただ話を聞いてもらうことで、精神的に孤立せずに不登校の問題と向き合え、子どもと一緒に乗り越えることができました。
どうか、保護者の方々も誰かを頼るなどして、一人で抱え込まないでください。お父さんお母さんが苦しそうにしていると、子どもも苦しいと感じてしまうこともあるので、親もSOSを出せるといいですよね。
頼れるところは遠慮なく頼って、親子一緒に乗り越えていく経験が、子どもの生きる力を育みます。
取材・文/水谷映美 編集/石橋沙織(キッズネット)