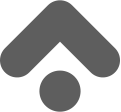【デフリンピックとは】競技の工夫や特徴、パラリンピックとの違いは?

デザイン・SMILES FACTORY
デフリンピック 日本で初開催へ
「デフリンピック」を知っていますか? 「耳が聞こえない・聞こえにくい」という意味の英語「Deaf」と「オリンピック」を組み合わせた言葉で、聴覚障がいのある選手たちによる国際的なスポーツ大会です。1924年から100年近い歴史があり、2025年11月には、日本で初めて開催されます。
聴覚障がいの選手が参加
デフリンピックは、ふつうの話し声くらいの音が聞こえない、聴覚障がいがある選手が参加できる国際的なスポーツ大会です。夏と冬にそれぞれ4年に1度開かれます。
障がい者の大会で知られるパラリンピックは身体・視覚・知的障がいのある選手が参加でき、聴覚障がい者はふくまれていませんが、耳が聞こえないことはスポーツをするときにも影響があります。体のバランスを取りにくいことや、プレー中の情報量が少ないことです。会話や合図、風の音やボールを打つ音などもスポーツには重要な情報ですが、それらを得ることができません。
プレー中は補聴器はずす
デフリンピックでは「聞こえない」ことを公平にするため、プレー中は補聴器をはずします。多くの競技で基本的なルールは聞こえる人のスポーツと同じですが、一部で工夫があります。例えば審判が選手に合図をするとき、バスケットボールやサッカーでは、笛だけでなく旗をかかげます。バレーボールではネットをゆらして知らせます。陸上や水泳では、スタートを光で知らせます。
陸上では「位置について・用意・ドン」を光で表す装置「スタートランプ」が使われます。22年のブラジル大会では、東京都立中央ろう学校(東京都杉並区)の陸上部顧問、竹見昌久さんが、スポーツ機器メーカーと開発したスタートランプが使われました。
竹見さんは、一般の大会に出た生徒が、スタートに出おくれてくやしい思いをするすがたを見てきました。そこで、ピストルと連動して光り、足元でじゃまにならない小型の装置を作りました。「日本でのデフリンピック開催をきっかけに、スポーツの場だけでなく街や人の工夫や配慮も、より進んでいってほしい」と話します。
考えよう
生活の中で耳の不自由な人がこまることはどんなことだろう。また、それを助けるためにどんな工夫があるかな?
(朝日小学生新聞2023年10月9日付の記事を再構成しました)
取材・文/奥苑貴世(朝日小学生新聞)