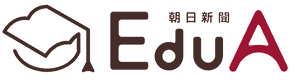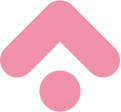日々のニュースの中に「学び」のきっかけがあります。新聞を読みながら、テレビを見ながら、食卓やリビングでどう話しかけたら、わが子の知的好奇心にスイッチが入るでしょうか。ジャーナリストの一色清さんがヒントを教えます。
※写真は、退陣表明をした石破首相の記者会見の様子=2025年9月7日、首相官邸、岩下毅撮影
1000日以上務めた首相は8人
石破茂総理大臣が自らの決断で辞任することになりました。後任は10月に開かれる予定の臨時国会の冒頭で、国会議員の投票によって決まります。衆議院と参議院で結果が違えば、衆議院の結果が優先されます。石破総理は10月の臨時国会冒頭まで総理大臣を務め、そこで正式に退任することになります。石破総理が就任したのは2024年10月1日なので、在任期間はほぼ1年となります。
石破総理は短命になりますが、日本の総理大臣には短命で終わった人がたくさんいます。戦後、日本には石破総理を含めて36人が総理大臣の椅子に座りましたが、このうち1000日(約2年9カ月)以上務めた人は8人しかいません。もっとも長いのは安倍晋三氏(06年9月~07年9月、12年12月~20年9月)の3188日で、次いで佐藤栄作氏(64年11月~72年7月)の2798日です。500日(約1年4カ月)以内で終わった人が半分近い16人もいます。もっとも短いのは、戦後すぐの東久邇稔彦氏(45年8~10月)の54日で、羽田孜氏(94年4~6月)は64日、石橋湛山氏(56年12月~57年2月)は65日、宇野宗佑氏(89年6~8月)は69日と続きます。
21世紀に入ると、さらに短命総理が目立つようになります。1980日務めた小泉純一郎氏(01年4月~06年9月)と安倍氏、1094日務めた岸田文雄氏(21年10月~24年10月)の3人を除けば、残る8人すべてが500日以内の在任期間となっています。ここにきて、菅義偉氏(20年9月~21年10月)が384日で終わったことや石破総理が短命で終わることから、1年くらいで次々にリーダーが代わる国という印象が再び強まっています。
国によって異なるトップの任期
総理大臣には法律で決められた任期はありません。日本国憲法67条では「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する」とだけ定められています。つまり、衆議院議員選挙があって新しい議員が決まったり、総理大臣が辞任表明したりすれば、国会で内閣が総辞職して国会議員による選挙で総理大臣が選ばれる仕組みです。これを首班指名選挙といいます。国会議員に当選し続け、首班指名選挙で選ばれ続ければ、憲法上はいつまででも総理大臣を続けることができます。
イギリスや日本など国会議員の中から総理大臣が選ばれる議院内閣制の国では、国会議員選挙や総理大臣辞任のたびに首班指名選挙でトップを選ぶ仕組みになっているため、特に任期を定めないのが一般的なのです。
一方、国民の直接選挙で選ばれる大統領制をとっている国の多くは大統領の任期を決めています。アメリカは1期4年で2期まで、韓国は1期5年で1期限り、フランスは1期5年で2期までとしています。大統領は強い権限を持ったトップなので、いつまでもその座にいると独裁になったり腐敗したりする心配があるためです。
リーダーの権力が強いロシアや中国のような専制主義国家でも、トップの任期を一応決めているのがふつうです。ただ、ロシアでは「大統領は1期4年で2期まで」と憲法で定められていたのですが、プーチン大統領が憲法を改正して最長2036年まで大統領を務めることができるようにしました。中国では国家主席の任期は2期10年と決められていましたが、習近平国家主席がその決まりを撤廃して3期目に入っています。専制主義国では、トップの力が強ければ自分の任期も自由にできるようです。
短命総理が増える状況の良さと課題
日本では、1955年の自民党結党以来、自民党が与党である期間がほとんどです。自民党の総裁がそのまま総理大臣になってきました。海外からは政治が安定している国と見える状況ですが、短命の総理が多くなっています。その理由はいろいろ考えられますが、よく言えば民主主義が機能しているためであり、悪く言えば国会議員が目先の選挙を気にしすぎるためではないでしょうか。
総理大臣は就任すると、国会で野党から厳しい質問を受けます。また、メディアは発言や行動を細かく報道します。世論調査をすると、最初は高い内閣支持率でスタートしますが、そのうち期待がはがれていき、支持率が落ちていくのがふつうです。そうなると、与党の議員や党員は次の選挙で負けるのではないかと浮足立ちます。実際に選挙で負けると、心配が現実になったということで、党首を代えてイメージ刷新を図りたいと思うようになります。次の首相を狙っているライバルはたくさん控えています。こうして総理大臣は追い詰められて辞任せざるを得なくなるというのが、よくあるケースです。
今回もそのケースでした。自民党は石破総理になってから衆議院でも参議院でも議席を減らして少数与党となったため、議員たちの心配が膨らんだのです。石破総理の自民党総裁としての任期は2年残っていましたが、多くの議員はそれを待てず、党内でおこなう総裁選挙を前倒しして新しい総裁に代えようという動きが強まったのです。
大胆な政界再編も必要か
ただ、自民党の新総裁が選ばれ、総理大臣になっても、少数与党であることは変わりません。法案を可決させるためには、野党の協力や連立参加が必要になります。その状況を変えようとして衆議院を早期に解散して自公が多数を回復したとしても、解散のない参議院は少数与党のままです。しかも、3年ごとに半数を改選する仕組みのため、3年後の参院選でよほど大勝しないことには解消できません。野党の協力が必要な状況は少なくとも6年は続くことが予想されます。
そう考えると、だれが総理大臣になっても政権運営は多難でしょう。短命の総理大臣がさらに続く可能性があります。こうした不安定な状態を解消するには、大胆な政界再編が必要だという声が聞こえてきます。
(2025年9月30日配信の記事を転載しました)