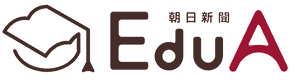日々のニュースの中に「学び」のきっかけがあります。どう話したら子どもの知的好奇心にスイッチが入るでしょうか。ジャーナリストの一色清さんがヒントを教えます。
※写真は、イスラエルと将来のパレスチナ国家が共存する「2国家解決」を議題にした国際会議で、映像で演説をするパレスチナ自治政府のアッバス議長=2025年9月22日午後、米ニューヨークの国連本部、田中恭太撮影
パレスチナ承認は約160カ国に
2025年9月21日から22日にかけて、パレスチナを国家として承認すると表明する国が相次ぎました。イギリス、フランス、カナダは先進7カ国(G7)として初めて表明しました。そのほか、オーストラリア、ポルトガル、ベルギー、ルクセンブルク、マルタ、モナコ、アンドラ、サンマリノが新たに表明しました。これでパレスチナを国家として承認する国は世界で約160カ国になりました。ただ、日本はイスラエルの後ろ盾になっているアメリカに配慮して国家承認をしていません。
パレスチナは中東のガザやヨルダン川西岸を領域にし、パレスチナ人による自治がおこなわれています。しかし、イスラエルが空爆や地上侵攻でガザを激しく攻撃し、多くのパレスチナ人が死傷しています。人道上の問題や中東のさらなる不安定化を心配する世界の国々が、イスラエルと将来のパレスチナ国家が共存する「2国家解決」による和平を実現させるために、国家承認に踏み切ってイスラエルに圧力をかけているのです。
「世界にはいくつの国がある?」の正解は…
この問題を理解する前提として、「国とは何か」ということを知る必要があります。まず問題です。「世界にはいくつの国があるでしょうか」。「正解は」と書きたいところですが、この問題に正解はありません。国として認めるかどうかは、それぞれの国の判断であるため、どの国の立場で数えるかによって答えが違ってくるのです。日本が国家承認している国は196カ国(日本を含む)です。だから、「日本から見ると」という前提をつければ196カ国が正解になります。ただ、国によって承認している国の数は違いますので、別の国から見ると別の数になります。
国際連合(国連)の加盟国数は、世界の国数の一応の目安になります。国連加盟国は193カ国です。日本の196カ国と差があるのは、日本が承認しているけれども国連に加盟していない国が四つあり、日本が承認していないけれど国連に加盟している国が一つあるためです。前者はバチカン、コソボ、クック諸島、ニウエです。バチカンについては宗教的な中立性を保つため、コソボは独立をめぐるセルビアとの争いの影響があるため、太平洋の島国であるクック諸島とニウエはニュージーランドとの深い関係があるため、国連に加盟していません。また、後者は北朝鮮です。1948年に北朝鮮が建国されて以来、日本とは外交関係がなく、拉致問題が解決していないこともあるため、日本は国家として承認していません。
国には三つの要素が必要とされています。「領土」と「国民」と「主権」です。国が治めるはっきりした領域があり、国を構成する人々が住んでいて、独立した政治権力があることです。この3要素が備わっているうえで他国から国家として承認されて、国際的には国と認められます。
複雑な国際政治情勢がからむ「正式な国」
ただ、国と認められるには、複雑な国際政治情勢も関わります。たとえば、台湾です。台湾は戦前、日本の植民地でした。明治時代にあった日清戦争で日本が勝利したことで清国(中国)から割譲を受けたのです。しかし、アジア太平洋戦争で日本が敗れ、国民党が治めていた中華民国の領土となりました。ただ、中国大陸では国民党軍と共産党軍との内戦が続いていました。49年には劣勢になった国民党軍が台湾に逃れました。そして台湾が中華民国となりました。大陸は共産党軍が支配し、中華人民共和国を建国しました。こうして、二つの中国が生まれたのです。
国連に最初に加盟したのは中華民国でした。45年に第2次世界大戦が終結した時、中国を代表していたのが中華民国だったためです。中華民国は戦勝国のひとつとして国連の安全保障理事会の常任理事国にもなりました。こうした状況から日本政府も中華民国を国家として承認し、圧倒的な人口と領土を持つ中華人民共和国は国連からも日本からも正式な国とは認められなかったのです。
しかし、中華民国より圧倒的に大きい中華人民共和国を国家と認めないのは不自然で、時がたつにつれ国家承認する国が増えていきました。そしてとうとう71年の国連総会で「中華人民共和国の代表が国連における中国の唯一の合法的な代表であることを承認する」という決議(アルバニア決議)が採択されました。「蒋介石(中華民国総統)の代表は追放する」という決議案も用意されていたため、その決議前に中華民国は国連を脱退しました。
この流れを受け、72年にアメリカのニクソン大統領が中華人民共和国を訪れ、少し遅れて日本の田中角栄首相も中国を訪れ、最高指導者の毛沢東氏や周恩来首相と会談しました。その後、両国は中華人民共和国を国家として正式に承認しました。こうして、国連や多くの国では「ひとつの中国」となり、台湾は一地域の扱いになりました。
ただ、今でも台湾を国家として承認している国があります。太平洋の島国であるツバル、マーシャル諸島、パラオ、中南米のグアテマラ、パラグアイ、ハイチ、ベリーズ、セントビンセント・グレナディーン、セントクリストファー・ネビス、セントルシア、ヨーロッパのバチカン、アフリカのエスワティニの12カ国です。台湾からの経済援助や技術支援を受けていたり、歴史的な関係があったりする国です。日本やアメリカも台湾との交流自体は続けており、中国が「ひとつの中国」を完成させようとして台湾を武力で併合することには強く反対しています。
「世界は一つ」の理想も
最後に、国が乱立する今の世界の形が最終の形ではないという考え方があることにも触れておきたいと思います。「世界連邦」という考え方です。第2次世界大戦後、国があれば国同士の争いが起こり、国連はそれを止めるには力不足だということを心配する人たちが世界にいました。そうした人たちが「世界がひとつの国になればいい」と考えて提唱し、それをめざす運動を始めたのです。ノーベル物理学賞を受賞した科学者のアインシュタイン氏や著名なイギリスの歴史学者であるトインビー氏、日本ではノーベル物理学賞を受賞した科学者の湯川秀樹氏、「憲政の父」とよばれた政治家の尾崎行雄氏、ジャーナリストで首相にもなった石橋湛山氏らも運動の積極的な賛同者でした。その高い理想に現実が追いつけそうにないため、今はかつての盛り上がりはありません。しかし、運動は今も続いています。
(2025年9月30日配信の記事を転載しました)

一色清(いっしき・きよし)さん
朝日新聞社に勤めていた時には、経済部記者、アエラ編集長、テレビ朝日 「報道ステーション」コメンテーターなどの立場でニュースと向き合ってきた。アイスホッケーと高校野球と囲碁と料理が好き。