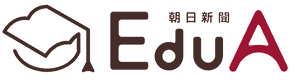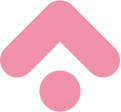日々のニュースの中に「学び」のきっかけがあります。新聞を読みながら、テレビを見ながら、食卓やリビングでどう話しかけたら、わが子の知的好奇心にスイッチが入るでしょうか。ジャーナリストの一色清さんがヒントを教えます。
※写真は、今年のノーベル賞受賞が決まり、スウェーデン大使館のレセプションパーティーに出席した大阪大の坂口志文・特任教授(手前)と京都大の北川進・特別教授=2025年10月13日午後7時7分、東京都内、後藤一也撮影
受賞した2人とも公立高校の出身
10月上旬、ノーベル賞の発表がありました。わたしたちの関心は日本人が受賞するかどうかということに集まりますが、2025年は2人の日本人が受賞しました。生理学・医学賞の坂口志文さんと化学賞の北川進さんです。これで日本人(日本出身で成人後に外国籍を取得した人を含む)の個人による受賞者は30人になります。(ほかに平和賞を受賞した日本の団体として日本原水爆被害者団体協議会があります)。
30人の部門別では、物理学賞がもっとも多くて12人、化学賞が9人、生理学・医学賞が6人、文学賞が2人、平和賞が1人です。経済学賞の受賞者はまだいません。理系の研究者が圧倒的に多く、ほかに作家が2人と政治家が1人という内訳になります。
受賞者の学歴には、かなりはっきりした特徴があります。今回の坂口さんは滋賀県の県立長浜北高校から京都大学医学部に進みました。北川さんは京都市立塔南高校から京都大学工学部に進みました。このように受賞者のほとんどが大学も高校も公立であることです。
卒業大学をみると、京都大学が10人、東京大学が9人、名古屋大学が3人で、埼玉大学、東京工業大学(現・東京科学大学)、東北大学、長崎医科大学(現・長崎大学)、北海道大学、神戸大学、山梨大学、徳島大学が1人ずつになります。すべて国立大学で、私立大学の卒業生は1人もいません。
卒業した高校(旧制中学含む)を見ると、30人のうち私立は2人だけです。1973年に物理学賞を受賞した江崎玲於奈さんが京都市にあった旧制同志社中学(現同志社中学、高校)、2001年に化学賞を受賞した野依良治さんが神戸市の灘高校を卒業していますが、ほかの28人はすべて都道府県立や市立の公立高校です。
高校の所在地を都道府県別にみても、意外なことが分かります。東京都の高校出身は1987年に生理学・医学賞を受賞した利根川進さん1人だけです。利根川さんは愛知県で生まれ、中学時代に東京に引っ越してきて都立日比谷高校に進みました。生まれも育ちも東京というわけではありません。日本の人口の1割以上を占め、開成、麻布、桜蔭などのそうそうたる進学実績を誇る高校があるので、もう少し受賞者がいてもよさそうなものですが、意外に少ないのです。逆に都道府県別人口ランキングで28位の愛媛の高校から3人、27位の山口の高校から2人の受賞者が出ています。
すぐに役立たない研究に取り組める自由さや懐の深さも
ノーベル賞受賞者に公立の出身者が多い理由はいくつか考えられます。まず、受賞者が高等教育を受けた時代は公立優位の時代だったということがあるでしょう。今回受賞した坂口さんと北川さんはともに74歳です。中学や高校に進学したのは1960年代です。すでに高い進学実績を誇る有名な私立の中学や高校はありましたが、今ほど優位だったわけではありません。特に地方では地元の公立中学から近くの公立高校に進むのがふつうのコースでした。
この2人より前に受賞した人たちの時代においてはなおさらでした。今のように都会への人口集中が進んでおらず、地方の過疎化が深刻になる前です。都市と地方との教育格差は今より小さかったといえます。
大学が公立ばかりである最大の理由は、研究環境にあったと考えられます。京都大学や東京大学には、優秀な教授や学生がおり、立派な研究施設があり、資金も比較的潤沢という環境がありました。すぐに役に立たない研究でも取り組める自由さや懐の深さがあったとも言われます。また、海外への留学や海外での研究にも国立大学名や人的なつながりが役に立つケースが多かったとみられます。
ただ、高校にしても大学にしても公立優位はゆっくりとではありますが、崩れています。ノーベル賞を受賞するには、大学卒業から50年くらい後になるのがふつうです。私立中高が受験戦線ではっきり優位に立って以降の人がノーベル賞を受賞するのはこれからになります。私立中高出身の受賞者が増える可能性はあります。大学にしても国公立大学と私立大学の環境格差は縮まっています。日本初の私立大学卒のノーベル賞受賞者が出るのはそう遠いことではないように思えます。
地道な努力も必要
最後に今回の2人の受賞者が大切にしている言葉が同じだったことにも注目したいと思います。それは「運鈍根」という言葉です。坂口さんはインタビューで好きな言葉として挙げ、北川さんは学生によく使う言葉として挙げています。運鈍根とは、物事を成功させるのに必要なのは、「幸運」と「才気走らず粘り強いこと」と「根気」の三つだという意味です。つまり、粘り強く、あきらめず、コツコツとやって、そこに幸運が舞い込めばうまくいくということです。2人は研究成果が認められない苦難の時代が長くあったことを明かしています。それでも自分を信じてコツコツと研究を続け、花が開いたのです。
研究で成果をあげるために必要なこととして、地道な努力を受賞者2人がともに挙げているということは、心を打ちます。2人からはひらめきの天才より努力の秀才のイメージが浮かびます。それはどこか地方の公立高校から国立大学に進む理系の学生のイメージと重なる気がします。