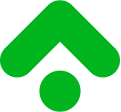昔からあるやり方で年賀状をつくろう

2020
年賀状 によく使 われる言葉
まずは
明 けましておめでとう:「新年 が明 けておめでたい」という意味 。賀正 :「正月 を祝 う」という意味 。迎春 :「新年 をむかえた」という意味 。昔 の暦 では、正月 は春 だったため。頌春 :「新年 をほめたたえる」という意味 。謹賀 新年 :「つつしんで新年 をお祝 いします」という意味 。あらたまった言 い方 。恭賀新年 :「うやうやしく新年 をお祝 いします」という意味 。あらたまった言 い方 。- Happy New Year:
英語 で「新年 おめでとう」の意味 。
このほかにもいろいろあるので
いも判

あぶり出 し
もうひとつ、
つくり
もらった
あぶり



筆 や筆 ペンもおすすめ