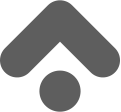熊の被害が増えるのはなぜ? 専門家があげる「人間社会の変化」

両手でつかんだクルミに口をつけるクマ=9月、秋田市 ⓒ朝日新聞社
ドングリ類が不作の地域は要注意
連日、クマによる被害が伝えられています。秋にクマのえさとなるドングリ類の不作が予想される地域では、人が住む地域に現れるクマがさらに増えることが心配されています。専門家は「クマとの付き合い方を考え直す時期にきている」と話します。
40年で分布が2倍に
4月から9月末までにクマの被害にあったのは、108人(速報値)。統計をとり始めて被害がもっとも多かった2023年度の同じ期間の109人に近いペースです。
クマについて研究している東京農工大学の教授、小池伸介さんは「この数年で急にクマが凶暴になったわけではない」と話します。小池さんの研究室などの調査では、この40年で本州にすむツキノワグマの分布は2倍、北海道にすむヒグマは1.9倍ほどに広がったことがわかりました。
その背景に「日本社会の変化」を挙げます。野生動物と人の生活地域の間にある「里山」が、人口減少などで手入れされず荒れてしまい、人とクマの暮らす境界線があいまいになりました。
ドングリなどが不作の年には、クマが冬眠前の秋、食べ物を求めて人里近くに現れることはありました。今年の特徴は、夏前から人里に現れるケースが増えたこと。理由は、はっきりとわからないといいます。「例年とちがう気象条件になると、クマが食べる植物の成長具合が変わることも。一時的に山の中で食べられるものが減ったため、人里に近づいてきた可能性が考えられます」
人の近くに現れないような環境作りが大切

各地で対策が進められています。栃木県矢板市は、市内の小学生全員にクマよけの鈴を配ることにしました。
9月1日から、住民の安全が確認できた場合などに、人里に出たクマを自治体の判断でうてるようになりました。山形県鶴岡市では9月20日、市街地に現れたクマをうつことを市長が許可。全国で初の判断となりました。ただ、その直後にクマが動き出し、安全が確保できなかったため、これまでと同じく警察官の命令のもと駆除されました。
「自治体の負担を考えると、野生動物の知識を持つ職員を配置していかないと、うまくまわっていかないのでは」と小池さんは指摘します。
「駆除は最終手段であり、クマが山から出てきた時点で人間の負け」と強調します。生ごみをきちんと管理したり、収穫しない柿の木をなくしたりするなど、クマが人の近くに現れないような環境を作ることが大切といいます。

取材・文/佐藤美咲(朝日小学生新聞)
(朝日小学生新聞2025年10月9日付)