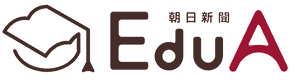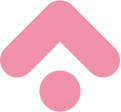子どもが寝ているとき、ひどいいびきをかいていたり、「呼吸が一瞬止まった!?」と不安になったりしたことはありませんか。その症状はもしかすると、睡眠時無呼吸症候群かもしれません。子どもの無呼吸を疑った時、どのように診察や治療を受ければ良いのでしょうか。昭和大学病院付属東病院睡眠医療センター長で医師の安達太郎さんに、症状や受診のポイントを聞きました。
居眠り指摘され受診も
――子どものいびきの危険性について教えてください。
お子さんがいびきをかく直接的な原因は、口呼吸です。人間は、口を開かないといびきをかくことはできません。特に仰向けで寝たときに口が開いていると、重力で軟口蓋(なんこうがい、口腔〈こうくう〉の天井奥にあるやわらかい部分)や舌の付け根が落ち、気道が閉塞(へいそく)しかかっていびきをかいてしまうのです。それで大人のように呼吸が止まってしまう睡眠時無呼吸症候群は、子どもであってもあり得ます。
私たちの睡眠医療センターにいらっしゃる患者さんの中ではそれほど多くありませんが、睡眠時無呼吸症候群の中で数パーセントがお子さんであると言われています。2、3歳の小さなお子さんから小中学生まで年齢層もさまざまです。
――お子さんのどんな気づきから受診を考えられるのでしょうか。
子どものいびきを不安に思い、受診されるケースが一番多いです。そのほか、首を伸ばした苦しそうな寝姿が気になる、息を吸い込むときに胸の一部がへこむ陥没呼吸が気になるといったことから相談する人もいます。子どもがイライラして怒りっぽくなり、睡眠の問題を疑って受診する人もいます。
お子さんが自分から眠気のことを伝えるケースは少ないように思います。学校の先生から授業中の居眠りや、集中力の欠如などを指摘されて気づく人もいます。大人とは症状の訴え方が少し異なることも特徴で、なかには食欲のなさを訴えるお子さんもいます。
――どのタイミングで受診を考えると良いのでしょうか。
親御さんが「心配だな」と感じたタイミングで、まずはかかりつけの医師に相談しましょう。基本的には耳鼻科で良いと思いますが、落ち着きのなさなど行動面が気になる場合は小児科を受診してもかまいません。状況に応じて、専門の大きな病院を紹介されると思います。
夜間のいびきが気になり、成長が悪くて身長が伸びない、集中力がない、学校から日中の眠気を指摘された、というケースについては、すぐに受診をおすすめします。治療もすぐに手術になることはまれで、治療法にはさまざまな選択肢があります。お子さんの成長という観点からよりよい選択を医師と考えていきましょう。
原因となる疾患を取り除く治療
――子どもの無呼吸はどのように診断するのでしょうか。
大人の場合は10秒以上の無呼吸が1時間あたり5回以上という定義がありますが、子どもの場合は明確な定義がありません。普通の呼吸が少し止まっているような状態でも、それを無呼吸として診断します。
その理由に、お子さんの症状が多様であることがあげられます。大人であれば、日中の眠気、中途覚醒、夜間頻尿、朝方の頭痛など明確な症状があります。ですが、お子さんの場合は落ち着きがない、日中ボーッとしている、口呼吸、イライラ、陥没呼吸、寝相が異常に悪く呼吸が苦しそうであるなど、人によって訴えが広く、重症度の判定をすることがとても難しいのです。
――診断には検査などを行いますか。
子どもの場合、入院をして精密検査まで行うケースはごくまれで、自宅で行う簡易的な睡眠検査を行うのが一般的です。寝ているときに、指先にパルスオキシメーターを、鼻にもエアフローセンサーという機器をつけ、呼吸の状態、いびきの音、血中酸素などを測定します。
簡易睡眠検査のイメージ。指先にパルスオキシメーターを、鼻先にエアフローセンサーをつけて測定する=安達医師提供
ですが、小さなお子さんの場合はこうした装置をつけて寝ても外してしまうことも多いです。こうした検査は補助的な診断材料として扱い、ご家庭での状況をお聞きしたり、おうちで寝ている姿を撮影した動画を確認したり、耳鼻科や内科的な疾患が隠れていないかを診たりしながら、睡眠時無呼吸症候群と診断して治療を進めていくことになります。
――子どもの睡眠時無呼吸症候群を引き起こす原因にはどのようなものがありますか。
お子さんの場合、扁桃(へんとう)やアデノイドの肥大、アレルギー性鼻炎などの耳鼻科的な疾患が口呼吸を引き起こし、無呼吸のリスクとなることが多いです。あごの小ささや肥満など外見的な特徴も気道をふさぐリスクを高めます。
大人の場合は、睡眠時無呼吸症候群が原因となって、動脈硬化が起こり、高血圧、心筋梗塞(こうそく)、脳梗塞といった病気につながっていきます。なので、その元になる睡眠時無呼吸症候群を治療します。ですが、お子さんの場合は何か原因があって無呼吸が起こるという点が異なります。お子さんの場合はその原因になる疾患をまずは治す必要があるのです。
――どのように治療を行いますか。
問題となっているのが耳鼻科と関連する疾患であれば、アレルギー性鼻炎の治療などで薬物療法を行うことが主流です。特にアデノイドは成長とともに小さくなっていきますから、薬で様子を診るパターンが多いと思います。
ですが、呼吸が苦しかったり、無呼吸が成長に著しい影響を及ぼしていたりする場合は、扁桃やアデノイドを切除する手術を早めに検討した方が良い場合があります。
外見的な特徴が原因となっている場合は、あごの大きさを矯正で広げるなど歯科的なアプローチが必要になることもあります。肥満が原因の場合は生活や運動指導などを行い、まずは適正な体重に戻すための治療が必要です。
大人の睡眠時無呼吸症候群の治療で有名な、マスクをつけて空気を送り込むCPAP治療はお子さんに適用することはほとんどありません。睡眠中に自分で取ってしまうことも多く、あまり効果が期待できないからです。
――無呼吸のお子さんが楽に眠れるように、自宅でできるケアの方法はありますか。
医師からも睡眠の体勢について指導をすることがあります。たとえば、枕を高くせず、横向き寝にすることを推奨しています。枕が高すぎると首が屈曲してしまい、いびきをかきやすくなるので、お子さんの寝姿を確認してみるとよいでしょう。
とはいえ、小さなお子さんの場合は親御さんが何度寝方を直しても、動いてしまうと思いますので、無理のない範囲で行いましょう。