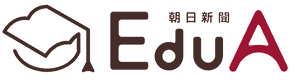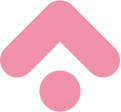日々のニュースの中に「学び」のきっかけがあります。新聞を読みながら、テレビを見ながら、食卓やリビングでどう話しかけたら、わが子の知的好奇心にスイッチが入るでしょうか。ジャーナリストの一色清さんがヒントを教えます。
※写真は、首相指名選挙が終わった後の与党党首会談の冒頭、握手を交わす自民党の高市早苗総裁(中央右)と日本維新の会代表の吉村洋文・大阪府知事(同左)=2025年10月21日午後4時19分、首相官邸、岩下毅撮影
自民・維新の連立政権が成立
高市早苗総理大臣が誕生しました。10月21日の国会の総理大臣指名選挙では、自民党のほかに日本維新の会などが高市氏に投票しました。
日本維新の会が高市氏に投票したのは、自民党と連立政権を組むことになったためです。自民党は衆議院でも参議院でも単独では過半数に届かないため、連立相手を求めていました。そこに自分たちが掲げる政策を実現させたい日本維新の会が歩み寄って連立が成立したのです。
日本維新の会と自民党が合意した政策はいくつもありますが、真っ先に実現させるとしたのが、「1割を目標に衆議院議員定数を削減する」というものです。1割は50議席弱です。削減の対象は比例区で選出される議席になるとみられています。12月中旬まで開かれる予定の臨時国会で成立を目指すことにしていますので、大急ぎで法案を作り、短期間の審議で採決にこぎつけないといけません。
削減は「身を切ることで政権の改革姿勢を示す」というメッセージが込められているようですが、削減に切迫した理由があるわけではなく、自民党内にも「選挙制度改革はすべての政党を巻き込んだ十分な議論が必要だ」という反対論があります。こうした状況から臨時国会で成立しない可能性もあり、その場合は政権自体が揺らぐことも考えられます。それくらい重要な法案になりますが、そもそも今の選挙制度がどうなっているのかを知らない人も少なくないと思います。今回は、衆議院議員の選ばれ方について説明します。
選挙で議員が選ばれる仕組みは
衆議院議員の定数は465人です。1983年には512人でしたが、92年に511人、93年に500人、2000年に480人、14年に475人、17年に465人と徐々に減らしてきています。今の定数は日本国憲法施行後、もっとも少ない人数です。 また、先進国が加盟している経済協力開発機構(OECD)によると、日本の衆議院議員の定数は人口100万人あたり3.7人で、同じ第1院で比べると加盟38カ国中36番目に少ないそうです。定数の465人のうち289人が小選挙区選挙で選ばれる議員で、176人が比例区選挙で選ばれる議員です。
選挙区というのは、選挙をするために有権者を一定の区域ごとに分けたものです。その区域で立候補した候補者が得票数を競います。選挙区には区域の広さに応じて、一般に大選挙区、中選挙区、小選挙区と呼ばれる3つの選挙区があります。
大選挙区はたとえば日本全体をひとつの選挙区にするもので、かつて参議院議員選挙では100議席を全国区の選挙にしていました。当選者は特定の地域にしばられないため視野が広くて学識のある人が選ばれるとして導入していました。ただ、知名度の高いタレントや業界団体の代表などが有利なことやお金がかかることなどから1980年に廃止されました。
中選挙区はひとつの選挙区から2人以上の当選者が出るように区割りされた選挙区のことです。日本の衆議院議員選挙では1993年まで都道府県を複数の区に分けて、ひとつの区から3~5人の当選者が出る中選挙区でおこなわれていました。しかし、与党で選挙に強い自民党はひとつの選挙区に複数の候補者を立て、野党各党はほとんどの選挙区で候補者を1人しか立てず、政権交代が起こりえない状況が続いていました。また、自民党候補者同士の競争が激しく、お金の力や地元への利益誘導がカギを握る選挙となっていました。
今の仕組みのメリットとデメリット
そうしたことから、1994年に選挙制度改革がおこなわれ、選挙区を小さくして1人しか当選しない小選挙区制に変えました。そうなると基本的に与党候補と野党候補の1対1の対決構図ができ、情勢次第では勝敗が一方に大きく傾き、政権交代が起きる可能性も出てくると考えたのです。また、選挙区が小さくなるため、かかる費用も少なくてすみます。
ただ、デメリットもあります。投票がまったく生かされない「死票」が多くなるのです。また、小政党からは当選者を出すことがとてもむずかしくなります。このデメリットを小さくするため、同時に比例代表制も導入しました。「小選挙区比例代表並立制」といいます。投票所では、小選挙区で「人」に投票し、比例区で「政党」に投票します。比例区は、政党の得票数に応じて各党に議席が配分されます。比例区は全国を11ブロックに分けています。政党はブロックごとにあらかじめ名簿を提出し、その名簿順位に従って当選者が決まるわけです。比例区では「死票」は少なく、小政党でも当選者を出すことができます。
ただ、今の小選挙区比例代表並立制ではおかしなことも起きます。小選挙区に立候補した人を比例名簿に載せることができるのです。「重複立候補」といいます。名簿では重複立候補者を同じ順位に並べることもできます。小選挙区で負けた人でも負け方が惜しかった人は、比例区のほうで当選することができます。負けた候補者の得票数をその小選挙区での最多得票者の得票数で割った数字を「惜敗率」といい、比例の当選者数の範囲内で惜敗率の高い順に当選していくのです。こうして小選挙区で負けたのに、比例区で復活当選するという現象が起こります。選挙に敗者復活戦があるようなもので、「変な制度」と感じている人は多いと思います。
想定するのは比例区の削減か
こうしたことや小選挙区の削減は調整がむずかしいことから、自民と維新は比例区の定数削減を想定しているようです。ただ、それは少数意見を代弁する少数政党に不利になる変更です。国会には多様な主張があったほうがいいと思います。選挙制度についてはこれまで時間をかけて議論し、多くの政党の理解を得て変更してきています。今回のように政権与党が短時間の勢いで決めようとするのは、あまりに乱暴ではないでしょうか。