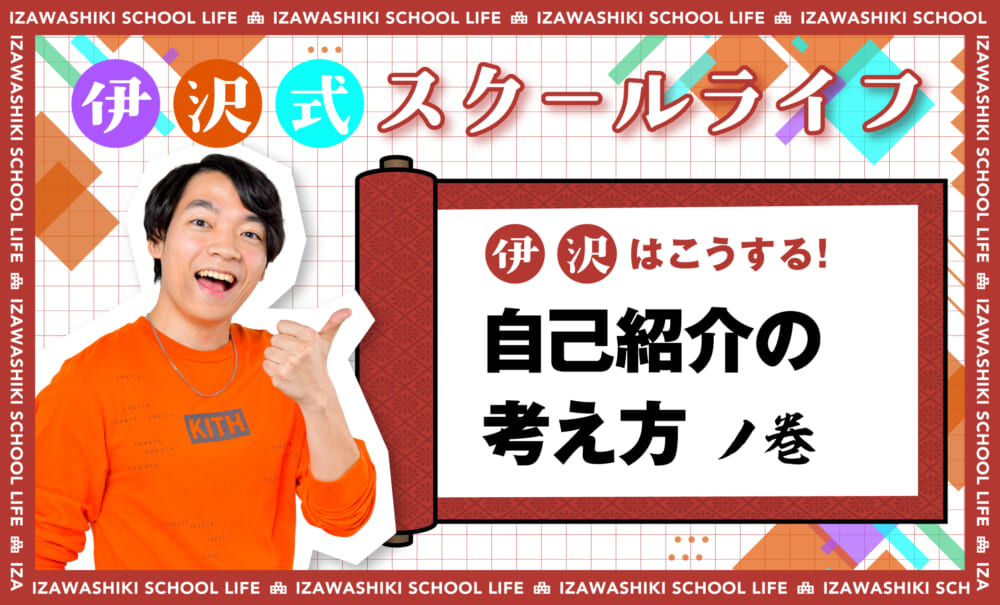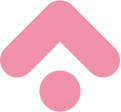「自由研究」は学び方を学ぶ。「つまらない」「うまくいかない」ことへの問いかけこそが最大の学び【伊沢式スクールライフ第2回】
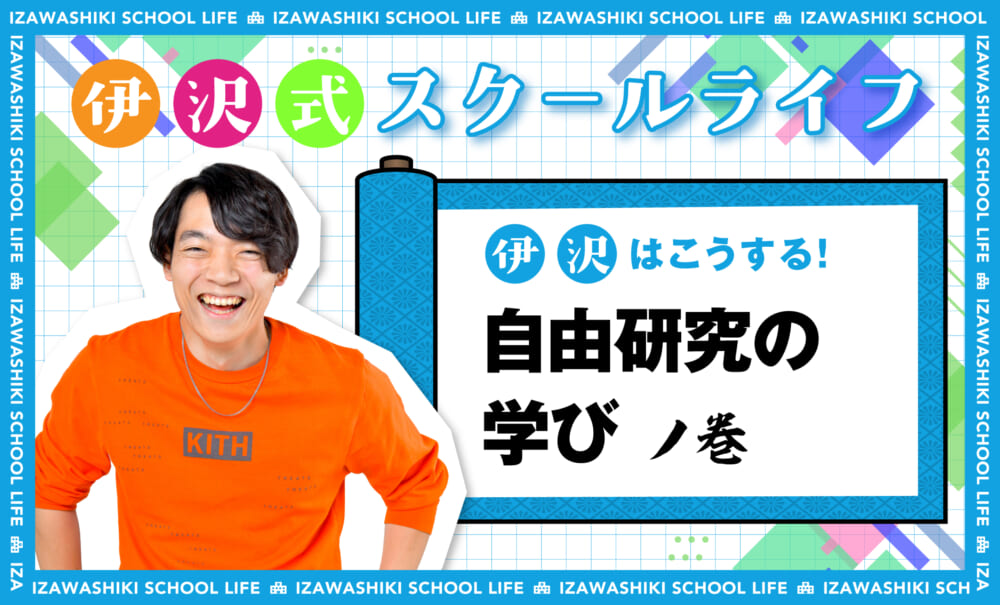
夏休みといえば「自由研究」という大きな課題が待ち受けています。毎年、テーマや関わり方に悩むという家庭も多いかもしれません。
この連載では「学校生活」をテーマに、QuizKnockの伊沢さんに、子どもの頃の思い出とともに、子どもたちや保護者に伝えたいメッセージをうかがっていきます。
第2回目のテーマは、「自由研究の学び」。自由研究が得意そうに見えて、じつは苦手だったと語る伊沢さんに当時を振り返りながら語っていただきました。
自分の知りたいことを自主的に探究するのが「自由研究」
自由研究は得意というより、むしろ苦手だったと思います。いちばん記憶に残っているのは、小学校3年生のときの夏休みの課題かな。
世界の国について調べるという内容だったのですが、みんなが知っているような国を取り上げるのはつまらないし、意表をつくところを狙って目立ちたいという気持ちもあったので、「セントビンセントおよびグレナディーン諸島」という国を選びました。めちゃくちゃインパクトがある名前でしょ(笑)。
夏休みのあとに、みんなが調べた国を先生が黒板に書き出して、「この中でみんなが知りたい国は?」とクラスで投票を行ったところ、見事に「セントビンセントおよびグレナディーン諸島」が1位に選ばれました。
知識でウケ狙いする、みたいな快感に目覚めた瞬間かもしれません(笑)。
「意表を突きつつ、テーマに沿った知識を武器に目立ちたい」という目的で、今自分が知りたいことをやり切った感覚は今でも強く心に残っています。
ただ、そのあとの自由研究はというと……親が選んだテーマで、親の力を借りて無難にまとめて済ませたことも多かったです。
今あらためて思うのは、自分の好奇心がまったく反映されていないものをまとめるよりは、評価は下がったとしてもやりたいことをやるべきだったな、と。
自由研究において一番大切なのは、その研究に自分の内側から湧き上がってくるモチベーションが含まれているかどうか。
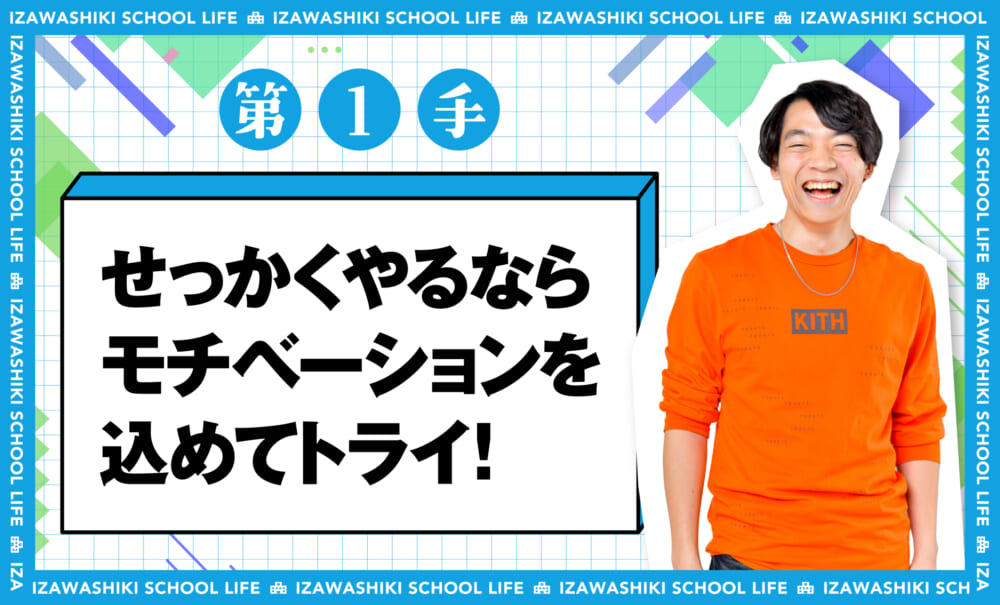
僕は失敗したからこそ、子ども自身が少しでも「おもしろそう」「知りたい」と思ったものに出会えたら、ぜひそれを題材テーマに選んでほしいと思います。
テーマ選びは真似から入っていい。むしろ研究の過程で浮かんだ疑問を大切に
テーマを選ぶとき、ゼロからスタートしなくちゃと考える人も多いかもしれません。ですが、それは大学生でも難しいことだと感じていて。ハードルを上げすぎるときついので、真似から入るで十分だと思っています。
たとえば、自由研究のテーマ一覧などを見て、やりたいことを探してもいいし、誰かがやっていた実験と同じ実験を試してみる。
「なぜ同じ結果にならないのだろう?」など、やってみたら新しい考えるタネが見つかることもありますから、困ったら真似してとりあえずやってみる、みたいなことも大切です。
今はテーマ探しで参考になるようないいサイトもたくさんあります。昔に比べて本質的な自由研究がやりやすくなっているのではないでしょうか。
〈伊沢さんが学研キッズネットの中でおすすめするなら?〉
■コーヒーがピンチ!? アイデアマップで考えよう
おすすめポイント:アイデアマップが自由でいいですね。疑問を見つけたり、好きな分野を見つけたりするのにとても役に立つ発想が紹介されていると思います。
■ピクトグラムは世界のことば
おすすめポイント:絵を描くのが好きな子におすすめ。自分が作ったピクトグラムと家族やお友だちがつくったピクトグラムを比べて、どちらが課題を解決できたかなど、ゲーム感覚で楽しく比較実験をするのに向いていると思います。
■立体模型をつくろう
おすすめポイント:つくるのが楽しくて、子どものモチベーションにつながりやすそう。理論的な背景が難しいから大人のナビゲートに工夫は必要ですが、モチベーションが高い状態でやってみようと子どもが思えるのはすごくいいですね。
「自由研究」のゴールはいい結果を出すことではない。大切なのは「なんでうまくいかなかったんだろう?」と問いかけること
大人はついつい、子どもの取り組みを見て、きれいにまとめようと手を出しがちですが、「いい結果」が自由研究のゴールではありません。
「実験の結果がうまくまとまらないのはなんでだろう?」「真似っこしたのに、なんで自分はうまくいかなかったんだろう?」という問いにこそ、学びの意味があると感じています。
そもそも自由研究は「自由」と言っているくらいですから、提示されたルールは守り、ときには他の研究を真似しつつも、よくできた「形」に囚われすぎてはいけません。少なくとも結論部分は。
「なんでうまくいかなかったんだろう」をゴールにしてもいいし、「じゃあ、この先どうすればいいのかな」という声かけを大人ができるなら、それもあり。もちろん、子ども自身がそれに気づけばすごくいいですし。
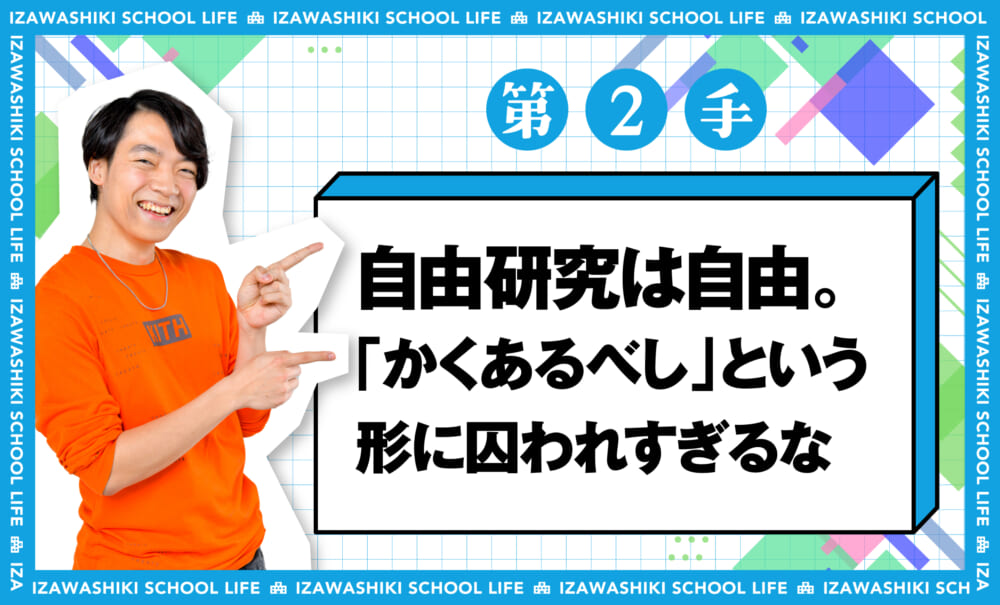
紆余曲折があって迷って迷って、いろんなことに出会っているうちにさまざまな疑問が出てきて研究が深まっていく……。
それは理想的な形ですが、そう上手くいくわけでもありません。お手本から学びつつ、お手本のようなきれいさにとらわれず「まずは研究してみること」そのものを優先しましょう。
研究の内容をきれいにまとめることよりも、「自由研究を通して学び方や調べ方を学ぶ」という、学びの本質を大事にしながら取り組むのがいいのではないでしょうか。
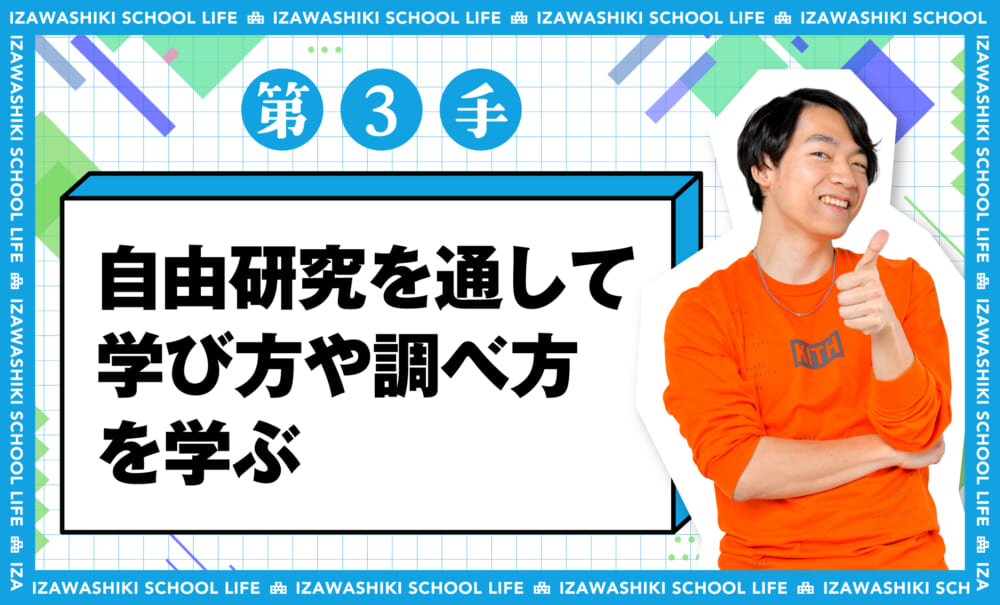
もし僕が今、自由研究をするとしたら? 自由研究って、どんなスタイルもありなんだと知っているし、学びの楽しさも大人の僕は気づいていますから、やりたいことはいっぱいありすぎて尽きません(笑)。
取材・文/森下真理 編集/石橋沙織(学研キッズネット) 写真/鈴木謙介 デザイン/曽矢裕子