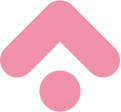1人1台のタブレットで学校はどう変わるのか 品川区の公立小学校で、ICTを活用した学習にとりくむ/シリーズ「専門家に聞く!」【第4回・その3(全5回)】

IC推進校を指定し、学校のICT環境を整え、1人1台のタブレットで学校と家庭で学習する「トータル学習システム」を構築した品川区。開始から2年、いまどんな課題が見えてきたのでしょうか? また、実際に子どもたちを前に授業を実施してきた第四日野小で感じている運用上の問題は?
2年間運用してきて、一番の課題は「ネットワーク」
−−プロジェクターやタブレットなど、ICTを活用した授業をするにあたって、運用上問題となることはありますか?

品川区教育委員会事務局指導課 統括指導主事 山本修史さん
中学でやっているオンライン英会話では、常にネットワークを使うので、ネットワーク関連のトラブルがまだ見られるのが課題です。オンライン英会話というのは、フィリピンの講師と生徒が1対1で英会話をする授業なのですが、ネットワークが不調でつながらない、ヘッドセットで話している声が相手に聞こえない、というようなトラブルが起こっています。これには先生が対応するほかなくなってしまっているのが現状です。
この種のトラブルはなかなか解消できずにいまして、現状では同時接続は30台が限界かな、という印象です。本当は80台くらいを同時に接続したいのですが、今の環境だとまだ厳しい状況ですね。
高木副校長:
わたしたちの学校でも、授業中に発生するトラブルはネットワーク関係のものがほとんどです。授業のなかで、子どもの作品を先生が前の黒板にいっせいに映すことがあります。それをするには、30人のクラスであれば、30人のタブレットと先生のパソコンすべてが確実にネットにつながっているという前提条件が必要ですよね。
先生が全員の答えを黒板に映し出すときに、ネットにうまくつながらないことで「ぼくの答えが映らない」となると、どうしてもざわつきますし、先生がその子のところまで行って、表示できるようフォローしないといけません。それでもうまくいかなければ、その子のタブレットを先生が持って、みんなに見せるという形をとる。こういうことは多発しています。
——ネットワークに関する課題は、想像以上に大きいのですね。
すべての学校で1人1台のタブレットを使えるようになるのは、財政的に難しい
——端末に関して、何か課題はありますか?
山本さん:
なにせタブレットの配備には、かなりお金がかかることなので、品川区も現状では区が配布するタブレットをこれ以上増やすことについては未定となっています。区内全校へのタブレット配布については、今は難しい状況です。
というのも、全部の学校にタブレットを入れるとすると、ランニングコストだけでもかなりの費用がかかってしまいます。ありたがいことに品川区では教育費の予算が多いのですが、今すぐ全校に配備するのは難しいと思います。
将来の教育環境がどうなっているかはわかりませんが、もしかすると、タブレットの個人持ちが当たり前になって、小学校に入学したらノートを買うようにタブレットを個人で買って持ってくるのが当たり前になるかもしれません。
そして学校では、そのタブレットで学習できるよう、学校のICT環境を自治体が整える、というような状況になるかもしれません。そうなれば、もっともっと活用の幅が広がるのではないかと思っています。
——国は、今後は家庭負担の方向で考えたいと言っていますが…
山本さん:
そうなると、就学援助の対象にもなるでしょうし、タブレットも、もっと安くなってくるかもしれませんね。公立学校の間での不公平感の解消をするには、国に旗ふりをしていただくことがベターですね。
選択式から記述式へのブラッシュアップを期待
山本さん:
また、正直に言うと、タブレットを使った「トータル学習システム」の家庭学習のコンテンツの部分では、まだ改善が必要だと思っています。従来のやり方では家庭学習に意欲が向かなかった子にとっては、いまの選択式の方法でも、学校の復習という点では効果があると思います。
ただ、タブレットでする家庭学習は選択式なので、三択とか四択のなかから正解を見つけます。ですから、でたらめにやっても何回かやっていれば「当たる」んです。いままでのように問題集とドリルがあって、それを子どもがウンウンと考えて、ノートに書くやり方のほうが、学習としては質が高いんですね。タブレットは万能ではありません。いままでの宿題に完全にとって代わるかというと、まだまだですね。

品川区立第四日野小学校 高木圭一副校長先生
高木副校長:
家庭学習でも、算数なら数字を打ち込みたいですし、漢字なら実際に書かせたい。それは今後の教材のブラッシュアップに期待します。
——山本さん、島崎先生、高木先生、貴重なお話をありがとうございました。次回は第四日野小学校の授業風景をレポートします。
【関連記事】シリーズ「専門家に聞く!」
【第1回】必修化が決定した、小学生向けプログラミング教育とは?
【第2回・前編】プログラミング教育は未来への扉
【第2回・後編】パソコンを使わなくてもプログラミングは学べる! リンダ・リウカス氏のワークショップレポート
【第3回・前編】プログラミング教育についての素朴なギモン。プログラミング教育って何? 本当に子どもに必要なの?
【第3回・後編】プログラミング教育についての素朴なギモン。料理はプログラミングだ!
【第4回・その1】品川区教育委員会にきく、品川区が1人1台のタブレットを配ったわけ
【第4回・その2】子どもたちが15分間、しーんとして自習にとりくんでいるわけ
【第4回・その3】2年間運用してきて、一番の課題は「ネットワーク」
【第4回・その4】2年生の生活科「めざせ生きものはかせ」
【第4回・その5(最終回)】4年生の市民科「目ざせ発表名人~効果的な表現方法を学ぶ」