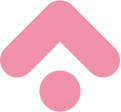小学6年生の約6割が携帯電話・スマホでネットをしている/データで読み解く、子どもとスマホ【第1回】
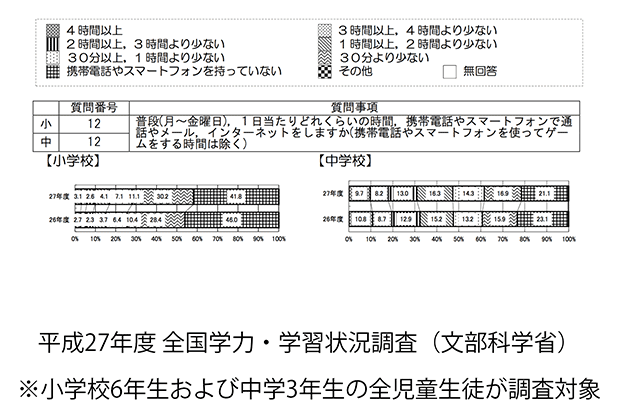
ガラケーからスマホへ、メールからLINEへ。わたしたちを取り巻くネット環境は大きく様変わりしてきました。このコーナーでは様々な調査結果や事例を通じて、スマホがある時代の子育てのヒントとなる情報をお伝えしていきます。
子どもの携帯電話やスマホ。小学校低学年のお子さんを持つ保護者の方にとってはまだ先のこと、中学生になるまでにじっくり考えたいと考える方も多いでしょう。ではこんな調査結果はご存じでしたか?
文部科学省が実施している全国学力・学習状況調査(※1)の最新調査によれば、全国の小学6年生で「携帯電話やスマートフォンを持っていない」と回答した児童は41.8%。小6の子どもの約6割が携帯電話やスマホを使って通話やメール、インターネットをしていることがわかっています。
いつの間にこれほど増えたのでしょうか。比較のために6年前のデータを見てみます。平成21年の同調査によると、「携帯電話を持っていない」と回答した当時の小6児童は69.1%(※2)。この6年間に小6時点で携帯・スマホを使っている子が倍増し、多数派になったことがわかります。
平成21年といえば、iPhone3GSが発売され、Twitterの流行の波が日本にやって来た年。日進月歩のITの世界、この間に大きくネット環境が変わったことは親世代も実感するところです。そんななかで、子どもたちが安全にネットやスマホとつきあっていくために、わたしたち親はいったい何をすればいいのでしょうか。
「スマホあり」の環境で子どもが育つという現実
キッズネット世代の保護者のみなさんが、スマホ関連の事件報道にふれたり、勉強そっちのけでスマホに夢中になっている子どもたちの姿をみたりして、「できればわが子にはスマホを持たせたくない」と思う親心は当然のことです。
しかしながら、内閣府の平成27年度青少年のインターネット利用環境実態調査によれば、高校生のスマホ利用率は93.6%で、昨年より約3ポイント増。(※3)
ほとんどの子どもが高校生になるとスマホを使っているのが実情です。
子どもたちはスマホのある青春時代を生きていくのだという現実を親世代が受け止めましょう。近い将来、子どもたちがスマホを手にしたとき、自分で安全な行動がとれるようにするには、どう導いていけばいいのか――このことを考えるのに、早すぎるということはありません。
親が見落としがちな「見えない」スマホ
とはいえ、小中学生には携帯電話やスマホは持たせない、また、安全のためいわゆるガラケーを持たせる方針なのでスマホは使わせない、という保護者の方も多いでしょう。子どもの安全をよく考えたうえでの方針で、愛情を感じます。
でもスマホという言葉の前に、「保護者の」「お古の」という形容詞をつけて考えてみてください。スマホ、本当に使っていませんか? 親端末の一時的な利用や、お古端末のWi-Fi利用に心あたりはありませんか? 東京都教育委員会の調査では、小学生の52.1%が「家で親や兄弟のスマホを使ったことがある」と回答しています。(※4)。
またWi-Fi環境下であればSIMを抜いたお古端末やiPod Touchでもネット接続できます。2020年東京オリンピック開催にむけて、無料で使えるWi-Fiスポットはどんどん増えていきますから、これらの「見えないスマホ」を使い、子どもたちが家の内外でネットにふれる機会はいくらでもあるのです。子どもがマイ・スマホを持っていないからといって、スマホに関する情報は何も教えなくていい、ということにはならないことがおわかりいただけると思います。
子どもの人生にスマホがあることを前提に、自分のものであれ借り物やお古であれ、その適切な使い方をしっかりと身につけさせることが新たに親の仕事に加わったと覚悟を決め、心の準備をはじめましょう。
となると、まず気になるのは当然「よそのお宅はどんなふうに使っているの?」ということですよね。次回はスマホ利用の内容やルールについて、データを読み解いていきます。
※1平成27年度全国学力・学習状況調査 調査結果のポイント(文部科学省)
平成27年度全国学力・学習状況調査 児童質問紙(文部科学省)
※2平成21年度 全国学力・学習状況調査 調査結果のポイント(文部科学省)
※3 平成27年度 青少年のインターネット利用環境実態調査(速報)(内閣府)
※4 平成26年度インターネット・携帯電話利用に関する実態調査報告書(東京都教育庁)
【関連記事】データで読み解く、子どもとスマホ
第2回 中学生、コミュニケーションはスマホで
データで読み解く、子どもとスマホ第1回から第10回まとめ
データで読み解く、子どもとスマホ第11回から第20回まとめ
データで読み解く、子どもとスマホ第21回から第30回まとめ
データで読み解く、子どもとスマホ第31回から第40回まとめ
データで読み解く、子どもとスマホ第41回から第50回まとめ
データで読み解く、子どもとスマホ第51回から第63回(最終回)まとめ