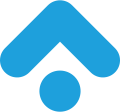用意 するもの
- ゴムねん
土 (またはねり消 しゴム ) 水 そう(または大 きめの容器 )- プラスチックのコップ 2こ
- わりばし
糸 水
実験 1
1
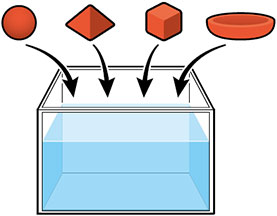
ねん土の形を変えて水に入れ、うくかしずむかを調べる。
2
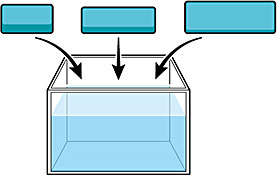
ねん土を平たくして、うくかしずむかを調べる。
3
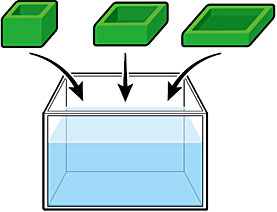
ねん土を箱の形にして、底の面積を変えて水に入れ、うくかしずむかを調べる。
4
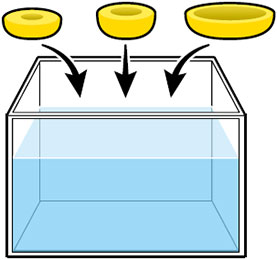
ねん土を船の形にして水に入れ、うくかしずむかを調べる。船の形は、いろいろ変えてみる。
まとめ方
実験の手順を書く。結果は表にまとめ、わかったことを書こう。
結果
ねん土の形とうきしずみ ねん土の底の面積とうきしずみ 船の形とうきしずみ
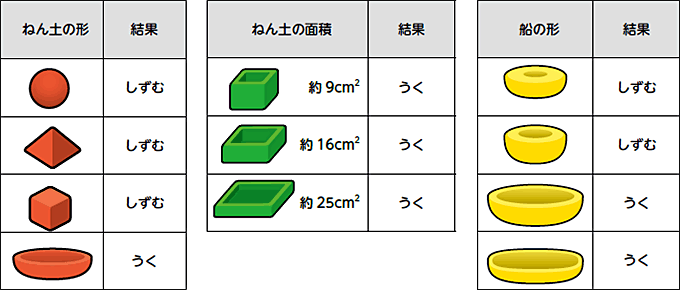
わかったこと
球 の形 では、大 きさを変 えても、うかない。- うすくのばしても、うかない。
船 の形 にするとうくことがある。うすく、全体 を大 きくすると、うきやすい。船 に水 を入 れると、しずむ。
実験 2
1
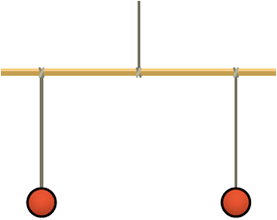
わりばしに糸をむすび、糸をつけたねん土をぶら下げる。糸の位置を調整して、つり合わせる。
2
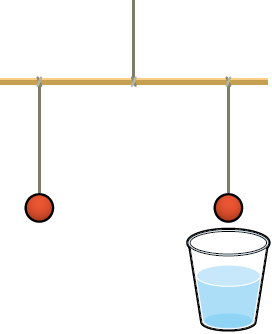
プラスチックのコップに水を入れ、片方のねん土を水に入れる。
どうなるかな。
3
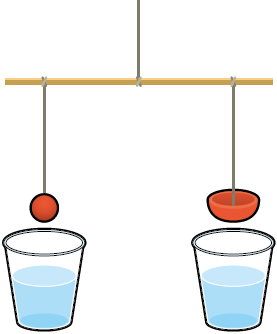
つぎに、ねん土の片方を船の形にして、両方を水に入れる。
どちらにかたむくかな。
まとめ方
実験の手順を書く。結果は表にまとめ、わかったことを書こう。
結果
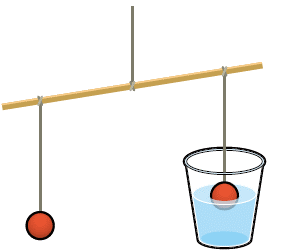
水に入れたほうが上がった。
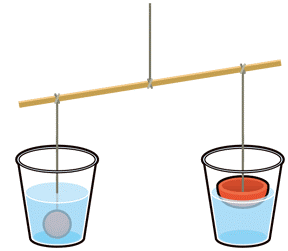
船の形のほうが上がった。
わかったこと
- ものを
水 に入 れると、そのものをうかそうとする力 がはたらく。 体積 の大 きいもののほうが、うかそうとする力 が大 きい。船 の形 にすると、体積 が大 きくなるので、うかそうとする力 が大 きくはたらく。球 の形 だと水 にしずむねん土 が、船 の形 にするとうくのはそのため。
「まとめ方のコツ 実験の例」を見てみよう
発展

船は、くらしや産業に必要なものを運ぶ、大切な役割をしているよ。
ものを運ぶ船には、どんな種類があるかを調べてみよう。
また、船にはどんな長所があるかを調べてみよう。
調 べ方
船に関する本を読んだり、ホームページを探したりしてみよう。
わかったこと
船 の種類

荷物を入れたコンテナという箱を積めるようになっている。

石油製品(重油、ガソリン、ナフサなど)を運ぶ。

セメントを、自動で積み降ろしできるようになっている。

強い圧力をかけてLPG(液化石油ガス)を運ぶ。

石炭や砂などを積み降ろしするためのクレーンがついている。

貨物を積んだトラックやトレーラーをそのまま運べる。
このほかにも、運ぶものに合った、さまざまな種類の船がある。
船 の長所
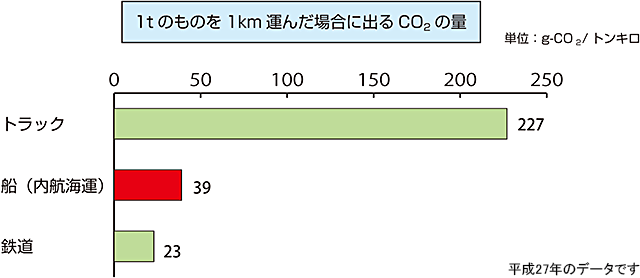
船 は、一度 に大量 のものを運 ぶことができるので、効率 がよい。だから、使 うエネルギーが少 なくすむ船 は、トラックに比 べ、地球 温暖化 の原因 になる二酸化 炭素 (CO2)を出 す量 が少 ない。
注意
実験 は、必 ずおうちの人 といっしょにしよう。- まわりがぬれたりよごれてもいい
場所 で実験 しよう。 実験 のあとは、おうちの人 といっしょに手 や道具 をきれいにあらい、しっかりあとかたづけをしよう- あらった
道具 は、きれいになったかどうかおうちの人 にたしかめてもらおう