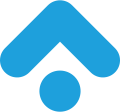用意 するもの

・びん(口が細いもの)
・ねん土
・ストロー
・絵の具
・水
やり方
●じゅんび
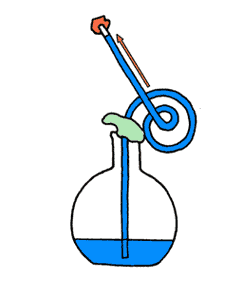
1)絵の具を水でといて、色水を作ります。それをびんに入れてストローをさし、びんの口のところにねん土をつけます。このときは、まだ、ねん土でびんの口を完全にふさがないでください。
2)水を吸い上げ、ストローの先を指でおさえて水位が下がらないようにします。
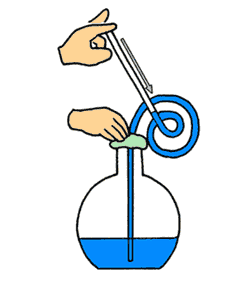
3)ねん土で、びんの口をしっかりふさぎます。ストローから指をはなすと、自然に水位が少し下がりますが、びんの中の水面より高いところで止まればだいじょうぶです。びんの口がねん土でしっかりふさがっていないと、中の水面のところまで水位が下がってしまいます。そのときは、もう一度やりなおしてください。
●やり方
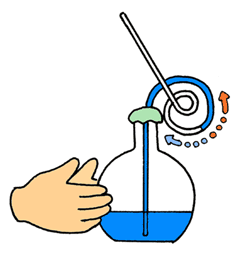
両手でびんを包みこみます。しばらくすると、びんの中の色水がストローの中を上がっていきます。手をはなすと、ストローの中の水がだんだん下がっていきます。

手で包みこまなくても、置き場所を変えると、まわりの温度変化によって、ストローの中の水面が上下します。部屋の中や戸外、日の当たるところと日かげなど、いろいろな場所に置いて、水面がどのように変化するか調べてみましょう。
なぜ、水面 が上 がったり下 がったりするの?
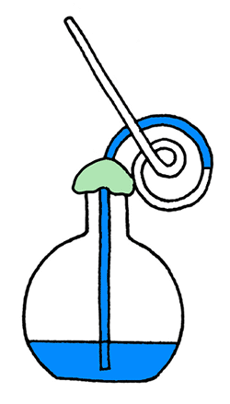
ストローをセットしたガラスびんをてのひらで包みこむと、びんの中の空気が体温で温められて膨張(ふくらむこと)し、びんの中の水を押します。すると、びんの中の水面は下がり、ストローの中に水を押し出します。だから、ストローの中の水面が上がるわけです。
手をはなすとびんの中の空気が冷えて収縮(ちぢむこと)し、ストローの中の水はびんの中にもどり、ストローの中の水面は下がります。
びんの中の空気の体積が200ml(ミリリットル)で、温度が10度変化したとすると、空気の体積の変化は約7mlになります。1cmの長さで1mlの容量のあるストローなら、7cmくらい水位が動きます。

びんといっしょに(本物の)温度計を置いて、いろいろな場所で温度をはかりましょう。実際の温度と水面の位置を確かめながら、ストローに目盛を書きこめば、「ストロー温度計」が完成します。
【関連ページ】100円ショップ大実験
■小型マッサージ機をせおってたわしが走り出す
■大気圧の助けをかりて完成!二階建てグラス
■えっ、なんで!?あみ目からもれない水
■園芸用の金属ネームプレートでボルタの電池作り
■くるくる回して急速冷とう「ひえひえマシン」
■100円化粧品で探偵ごっこ。アイシャドウで指紋検出
■グラスの底が凹レンズ「ガリレイ式望遠鏡」
■見えない力でゆれる「アルミホイルのぶらんこ」
■ものさしのすべり台からコインがジャンプ「コイン自動選別機」
■びっくりするほど飛び上がる「親子ボールの二段ロケット」
■ブルブル振動で科学マジック「ピンポン玉浮上」
■グラスをはなさないファイルシート「くっつきクレーン」
■コイル状のキーホルダーで「ハンディばねばかり」
■とってもカンタン、でもハマってしまう「おたま凹面鏡」
■ぶらんこの原理をたわしで研究「たわしの思い出ぶらんこ」
■ダンベルで学ぶ「回転モーメント」。どっちにころがる?
■洗面器を使ってえがく「声の振動模様」
■規則だったルールがおもしろい「ビー玉の追突実験」
■磁石はなぜ磁石なのかの実験「こなごな磁石」
■ふいてもふいても飛び出さない「じょうごの中のピンポン玉」
■時計をふり回して実験「目覚ましドップラー効果」
■コーヒーフィルターで色を分析「超かんたんクロマトグラフィー」
■超かんたん超軽量「クッション・グライダー」
■ひとりでに逆に回り始める逆回転!「超能力スプーン」
■発泡パワーで天までとどけ!「ペットボトル・ロケット」
■光のマジックボックス「ゴミ箱ピンホールカメラ」
■小型マッサージ機で歯ブラシが虫に変身!「歯ブラシ虫」
■大きいのと小さいの、どっちが強い?「風船の力くらべ」
【100円ショップ大実験】まとめ(1/3)
【100円ショップ大実験】まとめ(2/3)
【100円ショップ大実験】まとめ(3/3)